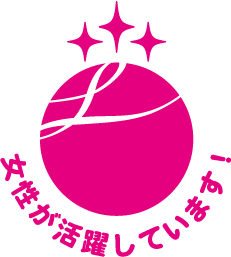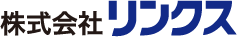熊本城 (犬塚)
熊本でお仕事の合間に
久しぶりに熊本城に行って見ました(*^_^*)
熊本城は加藤清正が築城記念にぎんなんを植えたことから 別名ぎんなん城とも言われています。
植える際にこの木が天守閣と同じ高さになった時何か起きると予言したそうです。
そして、同じ高さになった時に西南戦争が起こったそうですよ。
その銀杏もさぞかしキレイに色図いてると思いきや(@_@;)台風で葉っぱが落ちてました。
せっかく行ったのに(^_^;) でもたまにお仕事で行った先を散策するのもいいですね。
そんな余裕があればですが・・・
水戸名物(前川)
ミトホウモン
水戸といえば納豆ですが、
アンコウも有名のようで、早速
いただいて参りました!!
臭みも無く、あっさりしたお味で・・女性にとってはコラーゲンたっぷりでうれしいお鍋でした。
翌日は水戸から北上すること1時間
袋田の滝・・ダイナミック、というよりは、風情のある、水墨画のようなきれいな滝でした。11月初旬が紅葉の見ごろとの事、シーズンずれていても、たくさんの観光客でした。
博多に来たらこれを食べなきゃ (久保)
さわやかな季節になりました。
朝晩は肌寒いくらいですが、そうなると食べたくなるのが『鍋物』です。
博多で鍋というと…『もつ鍋』? いやいや、『水炊き』でしょう!
今夜は水炊きだ~という方のために、受け売りの薀蓄を少し。
博多に水炊きが誕生したのは享保年間。黒田藩の養鶏奨励政策で鶏卵を藩の専売品とし、
鶏の処分は自由としたため、それを食べるために水炊きが考えられたとか。
鶏肉のぶつ切りを水から炊いていく、素朴な調理法でした。
それをビジネスにして大成功したのが、今も博多に君臨する水炊きトップ3、
『水月』 『新三浦』 『長野』です。
『水月』は明治38年創業。鶏からスープを取り、そのスープで鶏肉を炊くという
新しい水炊きを考案して大ヒット。水炊きを本格料理に変身させました。
明治43年創業の『新三浦』はもとは遊郭でしたが、水炊きを名物とした料亭に業態を変え大繁盛します。
ちなみに『新三浦』のスープはにごっているので、発音もにごって「みずだき」です。
そして『長野』ははっきりとした創業は不明ですが、90年以上だとか。
この店は大衆路線を行くことで人気を集めました。価格の違いですが、
『水月』5,300円+税~ 『新三浦』6,800円+税~ に対し、『長野』は2,300円です。
こうして博多に根付いた水炊きですが、最近は新しい専門店も人気です。
ミシュランガイド福岡・佐賀2014特別版で紹介された『とり田』 『橙』、
日本全国のみならず、海外にも進出している『華味鶏』、
『長野』の暖簾分け『濱田屋』などなど。
…書いているうちに、食べたくなってきました。
博多にいらっしゃる方々、ぜひ一度水炊きを!